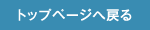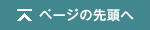�g�b�v�y�[�W���O�N�x���ƕ�
�ߘa6(2024)�N�x���ƕ�
| 1 | ���� | ||||||||||
| ������� | �ߘa6�N7��4���i�j�`5���i���j | ���@ AP �������d�F | |||||||||
| 2 | ������ | �N�R�� | |||||||||
| ��P�� | �ߘa�@�U�N�@�V���@�T���i���j | ��AP �������d�F | |||||||||
| ��Q�� | �ߘa�@�U�N�P�O���Q�W���i���j | ���k�C�� ��c���C�{�݃A�L��(�k�C��) | |||||||||
| ��R�� | �ߘa�@�V�N�@�Q���Q�O���i�j | ��AP �������d�F | |||||||||
| 3 | ��C������@�N�S�� | ||||||||||
| ��P�� | �ߘa�@�U�N�@�S���P�R���i���j | �����{���O�q������@�n�C�u���b�h | |||||||||
| ��Q�� | �ߘa�@�U�N�@�U���@�P���i�y�j | �����{���O�q������@�n�C�u���b�h | |||||||||
| ��R�� | �ߘa�@�U�N�P�O���@�T���i�y�j | �����{���O�q������@�n�C�u���b�h | ��S�� | �ߘa�@�V�N�@�P���Q�T���i�y�j | �����{���O�q������@�n�C�u���b�h | ||||||
| 4 | �S�����_�ی������Z���^�[�����c | ||||||||||
| �ߘa�@�U�N�P�O���Q�W���i���j | �i�k�C���j | ||||||||||
| ��@��u��c���C�{�݃A�L���v���n�C�u���b�h | |||||||||||
| 5 | �S�����_�ی������Z���^�[�������c�� | ||||||||||
| �ߘa�@�U�N�P�O���Q�W���i���j�`�P�O���Q�X���i�j | �i�k�C���j | ||||||||||
| ��@��u��c���C�{�݃A�L���v���n�C�u���b�h | |||||||||||
| 6 | �S�����_��ÐR�����E���_�ی������Z���^�[������c�i���J�Ȏ�Áj | ||||||||||
| �ߘa�@�V�N�@�Q���Q�P���i���j | ��@��@�A���J�f�B�A�s���J | ||||||||||
| 7 | ��s�s���� | �N�Q�� | |||||||||
| ��P��@�ߘa�@�U�N�@�V���@�S���i�j | ���@AP �������d�F | ||||||||||
| ��Q��@�ߘa�@�V�N�@�Q���Q�O���i���j | ���@AP �������d�F | ||||||||||
| 8 | �ϗ��R���ψ���@�ߘa6�N�x | �N�S��J�� | |||||||||
| ��P��@�ߘa�@�U�N�@�V���@�T�� | AP �������d�F�i�n�C�u���b�h�j(�Q���j | ||||||||||
| ��Q��@�ߘa�@�U�N�@�X���@�X�� | web�J�Ái�Q���j | ||||||||||
| ��R��@�ߘa�@�U�N�@�X���Q�T���`�X���R�O�� | ���ʊJ�Ái�Q���j | ||||||||||
| ��S��@�ߘa�@�U�N�P�Q���@�Q�� | web�J�� (�P���j | ||||||||||
| 9 | ���������Ɗw��\�� | ||||||||||
| �ߘa�U�N�x�@�������� | |||||||||||
| ���ߘa�U�N�x�n��ی��������i���� �u�ی���,���_�ی������Z���^�[�y�юs�撬�����Ƃ̘A�g�E�x���̂��߂�,�Ђ������葊�k�x�����H���C��̊J�Âƌ����v���S���ƎҁF�Җ{�N�m,�����ҁF���c�L | |||||||||||
| �����J�Ȍ��u�n�搸�_�ی���Õ����̐��̋@�\�����𐄐i���鐭���v�i������\�ҁF������j���S�����u���_��Q�ɂ��Ή������n���P�A�V�X�e���\�z�Ɋւ��錤���v�i���S�����ҁ@������s�j�������͎ҁ@�т݂Õ�C���ꐳ�i�A�ɓ���G�q�A�������b���A�ΐ�^�I���i���Z���^�[��t�j | |||||||||||
| �����J�Ȉˑ��ǂɊւ��钲���������Ɓu�ی�ώ@�̑ΏۂƂȂ����ˑ��ǎ҂̃R�z�[�g�����V�X�e���̊J���Ƃ��̓]�A�Ɋւ��錤���v�@���ƒS���ҁF���{�r�F�@�������͎ҁF�|�����C��{�G���C����M�q�C����C���ꐳ�i�C����_�C���c�B�m�C��{�݂���C���A�T�q�C���얾�N�C���������C�������C�|�щp���C�t�����C�����z��C���R�Ɣ��C�Җ{�N�m�C���鑏�C�������,�����_�i�C�R�����Y�C���c����Y,���i�~,���A�T�q,�����l��,�F�������],�ш̖�,��X���i,�X�T | |||||||||||
| �����J�Ȍ��u�n��ň��S���ĕ�点�鐸�_�ی���Õ����̐��ɂ�������@��Âɂ��x���̂��߂̌����v�i������\�ҁF����r�Ɓj���S�����u���I���@�Ɋւ�����Ԓ����v�i���S�����ҁ@������j�������͎ҁ@���c����Y | |||||||||||
| �����J�Ȉˑ��ǂɊւ��钲���������Ɓu�ˑ��ǎ҂ɑ���n��x���̐��̎��ԂƋςĂɊւ��錤���v���ƒS���ҁF���鑏,�������͎ҁF�u�c���a,���c�B�m,������,���R�Ɣ�,���c�L,��{�M��,�͖�ʉp,������,�т݂Õ�,�c����,��v�ۑ��q,�Җ{�N�m,�ɓ���G�q | |||||||||||
| ���ߘa�U�N�x�@�����J���ȁ@�M�����u�����ˑ��ǂ̎��ԂɌW�钲���E�������Ɓu�M�����u����Q����уM�����u���֘A���̎��Ԓ����v�������́G�S�����_�ی������Z���^�[���� | |||||||||||
| �����J�Ȍ��u���ʓI���L�����̍����W�c���_�Ö@�̎{�s�ƕ��y����ь��ʌ��̂��߂̌����v�i������\�ҁF���V���j���S�����u�G�r�f���X�̂���W�c���_�Ö@�̔ėp���̍����}�j���A���ƌ��C���ނ̊J���v�i�������S�ҁF���V���j�������͎ҁF�Җ{�N�m�C�F�J���� | |||||||||||
| �����J�Ȍ��u�Q�[���Ɋ֘A����������Q���̖��,�������鎾���y�т��̑Ή����̎��Ԕc���Ɏ����錤�� �v�i������\�ҁF�������j���S�����u�Q�[���Ɋ֘A�������k�Ƒ����̎��Ԓ����v�i�������S�ҁF�������_�E�_�o��Ì����Z���^�[�@������j�@�������͎ҁF���鑏,���c�L | |||||||||||
| �ߘa�U�N�x�@�w��\ | |||||||||||
| ����120����{���_�_�o�w��w�p����V���|�W�E�� �u���_��Q�ɂ��Ή������n���P�A�V�X�e���ɂ����鐸�_�ȂƐg�̉Ȃ̘A�g�v���F���c����Y,������s |
|||||||||||
| �ߘa�U�N�x�A���R�[���E�ˑ��֘A�w����w�p����@COVID-19���S���̐��_�ی������Z���^�[�y�і��Ԓc�̂̈ˑ��ǎx�������ɗ^���������I�e���̑��� �\4�N�Ԃ̒�����������\�@�ЎR�@�I,���鑏 | |||||||||||
| ����18����{���������NJw��@�V���|�W�E��5�@�u�s�A�T�|�[�^�[�̌���Ɖۑ�v �u���_�ی������Z���^�[�ɂ�����s�A�T�|�[�^�[�Ƃ̋����\���̌���Ɖۑ�\�v���c����Y |
|||||||||||
| ����18����{���������NJw��@�V���|�W�E��7�@�u���_�ȍݑ�x���ɂ����錻��Ɖۑ�v �u���_�ی������Z���^�[�ɂ��ݑ�x���̌���Ɖۑ�v���c����Y |
|||||||||||
| ��The International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) symposium [ Mental Health and high-risk behavior (delinquency and suicide) among young people in Cambodia and Japan] �gCurrent status and countermeasures for child suicide in Japan�hJunichiro Ota |
|||||||||||
| ����43����{�Љ�_��w��@�V���|�W�E��5 �u����̒n�搸�_�ی���Õ����̑��l���E���G���ɂ��čl����v���E�i��@�Җ{�N�m�F�u��s�s�̐��_�ی������Z���^�[�v�F�J����, �u���E��v�c����, �u�n���P�A�V�X�e���v������s, �u�R���f�B�J���Ɛ��_�ی������Z���^�[�v����_�� | |||||||||||
| ����120����{���_�_�o�w��w�p����V���|�W�E���@�ψ�����V���|�W�E��29 �u�e�q�E�w�Z�E�����̎x�����āH�F�@�ւ��z���ĂȂ���x���Ă����v�i��F��{�M���@�w�蔭���F�т݂Õ� |
|||||||||||
| �ߘa�U�N�x���� | |||||||||||
| �����O�q����� �P�j���W�@���X���X �@���_�ی������@�����@�u���_�ی������@�����ɂ����鐸�_�ی������Z���^�[�̖����v�@����_��i�a�̎R�����_�ی������Z���^�[�j �Q�j�n��ی������őO���i2024�N4�����j �u�Ђ������葊�k�x�����C��J�Â̌o�܂Ǝ��H -�ߘa4�N�x�n��ی��������i���Ƃ���-�v���c�L�i���挧�����_�ی������Z���^�[�j �R�j���i���� �@�i2024�N4�����j�u�ˑ��ǎ҂̐����ɒ��ڂ����x���̃l�b�g���[�N�Â���ɂނ��āv�I�� �x�q�i���ꌧ�����_�ی������Z���^�[�j �A�i2024�N5�����j�u���茧�́u8050�v���т̌���Ɖۑ�ɂ��āv���� �m��@�ق��i���茧���肱�ǂ��E�����E��Q�Ҏx���Z���^�[�����j �B�i2024�N6����)�u�u�����⑰�x���̂ǂ��v�ɂ�����x���Ɖۑ�ɂ��Ă̍l�@�v�������b�@���i�X�������_�ی������Z���^�[�j �C�i2024�N7�����j ���s�u���_�Ⴊ���Ғn�搶���ڍs���i���Ƃ̌���Ɖۑ�v�쑽�� �S���i���s������̌��N�Z���^�[�����j �D�i2024�N8�����j�u���l�s�ɂ�����[�u���@�ґމ@��x�����Ƃ�U��Ԃ��āv��J �S���q�i���l�s������̌��N���k�Z���^�[�j �E�i2024�N9�����j�u���猤�C�̐V���Ȏ��g�݁ie-���[�j���O���Ɓj�ɂ��āv�����@���q�i�k�C�������_�ی������Z���^�[�j �F�i2024�N10�����j�u���_�Ⴊ���҂��n��ň��S���Đ����𑗂邽�߂̎��g��-���_�ی������Z���^�[�ɂ��ی����E���̐l�ވ琬-�v�{�{���q(�F�{�����_�ی������Z���^�[) �G�i2024�N11�����j�u�Q�n���ɂ����鍂��҂̐��_�ی������@��23��ʕ�̓����ƍ���̒n��x���v���Ҋ�v�@���i�Q�n��������̌��N���k�Z���^�[�j �H�i2024�N12�����j�u�f�C�P�A�ɂ��������������x���Ɋւ���܂Ƃ߂ƍl�@�v��є��a�i�L�����������_�ی������Z���^�[����(��)�����x���ے��j �I�i2025�N1�����j�u���E�\�h�Q�[�g�L�[�p�[�{�����C���̐��ځ`���E�\�h�S���ŏ����ƂȂ������挧�̎��g�݁`�v�{�e���D�A���c�L�i���挧�����_�ی������Z���^�[�j �J�i2025�N2�����j�u�ً}�Ή�����̕��͂��猩���Ă������ƁF�[�u�ʕ�̌����Ƒ̐�������ڎw���āv�R�{�דT�ق��i���R�����_�ی������Z���^�[�j �K�i2025�N3�����j�u�����^���w���X�~���c�v�|�����i���s�������n�r���e�[�V�������i�Z���^�[�����j �� Katayama M, Fujishiro S, Sugiura K,Konishi J, Inada K, Shirakawa N, et al. Greater impact ofCOVID�]19 on peer�]supported addiction services than government�]owned services for addiction in Japan: a nationwide 3�]year longitudinal cohort study. Psychiatry ClinNeurosci Rep. 2024;3:e70012.https://doi.org/10.1002/pcn5.70012 |
|||||||||||
| 10 | �����J���Ȑ��_�E��Q�ی��ۓ��Ƃ̈ӌ������@���� | ||||||||||
| 11 | �Z���^�[������u��64���v���s�@�z�[���y�[�W���^�c�ψ��� | ||||||||||
| 12 | ��c���ւ̏o�� | ||||||||||
| (1) �S�����_��ÐR����A�����c��@(�N1��)�@( �Җ{�N�m�i�S�R�A����j�C���c����Y,���싳�l) | |||||||||||
| (2) ���_�ی��]���Ғc�̍��k��@(�N�U��)�@(����) | |||||||||||
| (3) DPAT�^�c���c��@(�N�Q��)�@(�Җ{�N�m) | |||||||||||
| (4) ���O�q�����ҏW�ψ���@(�N�U��)(�Җ{�N�m,���싳�l�C����C���ꐳ�i,����_) | |||||||||||
| (5) �A���R�[�����N��Q��W�҉�c�@(�N�Q��)�@(�u�c���a) | |||||||||||
| (6) �ˑ��ǐ���Ë@�֑��k�����S����c�@(�N�P��)�@(���鑏, �ɓ���G�q) | |||||||||||
| (7) ���_��Q�ɂ��Ή������n���P�A�V�X�e���\�z�x�����Ɓ@�A�h�o�C�U�[������c�@(�N�R��)�@(������s.�����_�i) | |||||||||||
| (8) �Ђ�������n��x���Z���^�[�S���A�����c�������@(�N�Q��)�@(���c����Y,�R�����Y) | |||||||||||
| (9) ���{���_�_�o�w�� �ЊQ�x���ψ���@(�N�S��)�@(������) | |||||||||||
| (10) ���{���_�_�o�w�� ���_�Ȉ�E���_�Ȉ�Â̎��Ԕc���E�����v��Ɋւ�ψ��� (�N8��)�@(�Җ{�N�m) | |||||||||||
| (11) ���{���_�_�o�w��@���_�ی������@�ψ��� (�N6��)�@ (���c����Y,��{�M��) | |||||||||||
| (12) ���̂����x���鎩�E�����i�Z���^�[������i�N2��j�i�Җ{�N�m�j | |||||||||||
| (13) �u�ˑ��ǂɊւ��钲���������Ɓv�L���҉�c�i�N1��j�i���鑏�j | |||||||||||
| (14) ���{���_�_�o�w��@���E�\�h�Ɋւ���ψ���i�����j�i���c����Y,��{�M��,��v�ۑ��q, �ɓ���G�q�j | |||||||||||
| (15) ���{���_�_�o�w��@�e�q�E�w�Z�E�����Ɋւ���ψ���i�N6��j�i�т݂Õ�,��{�M���j | |||||||||||
| (16) ���{���_�_�o�w��@�������_�Ȉ�Ì��C�ψ���i�����j�i�т݂Õ�,���c����Y�j | |||||||||||
| (17) �M�����u�����ˑ��Ǒ����i�W�҉�c�i�N2��j�i�Җ{�N�m�j | |||||||||||
| (18) �S�̃T�|�[�^�[�{�����Ɗ��E�]���ψ���_�i�N3��j�i�Җ{�N�m�j | |||||||||||
| (19) �u�����⑰�����x���邽�߂Ɂ`�����I�x���̎���v�̉����ɌW��L���҉�c�i�����j�i�Җ{�N�m�j | |||||||||||
| (20) ���_�ی���Õ����̍���̎{�����i�Ɋւ��錟����i�����j�i�Җ{�N�m�j | |||||||||||
| (21) �u�Ђ�������n��x���Z���^�[�E�����ւ̐l�ޗ{�����C�E�L��ꎮ�v���ψ���i�N�R��j�i�R�����Y�j | |||||||||||
| (22) ���{���_�_�o�w��@�����^���w���X�A�h�o�C�U�[���E�ψ���ψ��i�����j�i�R�����Y�j | |||||||||||
| (23) �u�ˑ��ǂ̕�����Ë@�֓��Ɏ�f�E���k���������̏��݂̍���Ɋւ��錤���v�����ψ���i�N�S��j�i���鑏�j | |||||||||||
| (24) �ߘa6�N�x�Љ�����i���Ɓ@�u�Ђ�������x���ɂ�����x���n���h�u�b�N�̍���Ɍ����������������Ɓv�i�N�S��j�i�R�����Y�j | |||||||||||
| (25) �ߘa6�N�x�Љ�����i���Ɓ@�u�����̂ɂ�����Ђ������葊�k�x���̎��{�Ɋւ�����Ԕc���y�ь��ʓI�Ȏ��{���@�Ɋւ��钲���������Ɓv�i�R�����Y�j | |||||||||||
| 13 | �����ψ���� | ||||||||||
| ���z�[���y�[�W�^�c�ψ��� �E�S�����_�ی������Z���^�[�ꗗ, �g�D�T�v�E����, ���ƕE���ƌv��, ���������Ȃ�,�z�[���[�W�ւ̃R���e���c�lj�������C �N�S����{�����D����, �u�S���̃Z���^�[�̐l���̐��E�@�\���v�̒����i����������j���s��, ���ʂ������p�y�[�W�Ɍf�ڂ���. |
|||||||||||
| �����쐬�ψ��� �E�ߘa�T�N�x�ɍs��ꂽ, ��c, �ψ����, ��������, �S�����_�ی������Z���^�[��������c��v���O�����Ȃǂ��f�ڂ���,�u����64���v��, �쐬�E���s����. |
|||||||||||
| 14 | �ۑ�ʈψ���� | ||||||||||
|
���蒠�E�����x����Ì����ψ��� �E���[�����O���X�g�ɂ��,�ʂ̉ۑ�Ɋւ���������E�ӌ����� �E�蒠�E�����x����ÂɊւ��錟����c�i�~�j�V���|�W�E���j�̊J�� |
|||||||||||
|
���ˑ��Ǒ�ψ��� �E�֘A��c�ւ̎Q�� �E���J�Ȉˑ��ǂɊւ��钲���������Ɓu�ˑ��ǎ҂ɑ���n��x���̐��̎��ԂƋςĂɊւ��錤���v�ɂ�����2�C���{,�S�����_�ی������Z���^�[�ɂ�����e��ˑ��ǑΉ��v���O�����̎��{�ȂNJ����̒���,�s�̖�E������,�喃�Ɋւ��鑊�k��������,�s�̖�ߗʕ���Ɋւ���C���^�r���[����,�g���E�}�A���h�o�C�I�����X�C���t�H�[���h�P�A�iTIVC�j���y�̎��g��,TIVC�����̖|��E���{�ꎑ���̍쐬�y�ѕ��쐬 �ESAT-G���C��2����{ �EVBP�Q���Z���^�[���ւ̎��g�� �E�ˑ��Ǒ��S�����_�@�ݒu�^�c���Ɓ@�Q�[���ˑ����k�Ή��w���җ{�����C�u�t�i���c�L,�u�c���a�j |
|||||||||||
|
�����E��ψ��� �E���N�J�Â������{���_�_�o�w��w�p����ł̃V���|�W�E�����J�Â��A�S���̐��_�ی������Z���^�[�ł̎��E�����Љ�邱�Ƃ��s���Ă���B2023�N6���ɂ́A��119����{���_�_�o�w���ɂ����āA�V���|�W�E���u�S���̐��_�ی������Z���^�[�ɂ����鎩�E��̎��g�݁v�ɂ�7���̐搶����e�Z���^�[�ł̎��E�����Љ�Ă��������A�W�҂Ƃ̊����ȓ��_�ƂȂ����B���N�x�̊J�Â͂Ȃ������A2025�N�͊J�Â��s���B�w��ł̔��\���e�́A�w��ɏ��^���f�ڂ��A���̌�A���{���_�_�o�w��ł̘_�������͂����Ă������ƂƂ���B |
|||||||||||
|
���ЊQ����������̃P�A���i�ψ��� �E���{���_�_�o�w��ЊQ�x���ψ���ɂ��V���|�W�E���u�ЊQ�h�����_��Ã`�[��DPAT��������10�N,���ꂩ��̍ЊQ���_�x���̉ۑ�ƓW�]�v�̊��ɋ��͂�,�V���|�W�E���ɂ����Ĕ��\���s���B �E�ЊQ�����_�ی���Ñ�ɂ����鐸�_�ی������Z���^�[�̖����Ɖۑ�ɂ���,�����c�����������s���B |
|||||||||||
|
�����_��Q�ɂ��Ή������n���P�A�V�X�e���ψ��� �E���_�ی��������k���u�K��̃I���f�}���h����̂���,���_�����̊�b�m���Ɋւ��錤�C������k�C��,�������s�̌��C�����Ɋ�Â�,�쐬�����B �E���̑�,�ɂ���Ɋւ�����ɂ��ă��[�����O���X�g�ɂď�L���s�����B |
|||||||||||
|
���f�[�^���ͥ�n�敪�͌����ψ��� �E�S�����_�ی������Z���^�[����̉��̂Ȃ����������,��,�����@��,�w�p�c�̓��ƘA�g����,�s���{���i���ߎw��s�s�j�ɂ�����n�搸�_�ی����̎��Ԃƃj�[�Y�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ̂ł����ՂÂ���ɍv�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B�ߘa5�N�x�Ɉ�������,�i�P�j�n�搸�_�ی��̗��j����,�i�Q�j�n��̎��E���͓��Ɋւ��鎿�⎆�����̕��͂ƕi���E��ψ���ƘA�g�j,�i�R�j�n�搸�_�ی��̌��J�������p�̐��i,�i�S�j���̑�,�ψ��̎��Ȕ��ӂɂ�銈���Ɏ��g�ށB�����ψ�����o�[�̂ق�,�I�u�U�[�o�[��,�㓡��s�搶�i�����ّ�w�j,�͖얫���搶�i���s�������n�r���e�[�V�������i�Z���^�[�j,�R���M�j�搶�i�������b���ȑ�w�j,���c�M�q�搶�i���m�i����w�j�Ȃǂ��}���Ċ�������B |
|||||||||||
|
���Ђ�������Ҏx�������ψ��� �E�n��ی��������i���ƂƂ��āA�Ђ������葊�k�x���Z�p�̌����ړI�ɁA�u�Ђ������葊�k�x�����H���C��vA���C���ΏہF�ی����E���_�ی������Z���^�[���AB���C�����茗�恄�AC���C���Ђ�������n��x���Z���^�[���AD���C���s�撬���A�n���x���Z���^�[�����J�ÁA�Ђ�������̗����E�x���A8050���A���B��Q���ɂ��Ă̍u�`���s�����B10�N�̎��ƌo�߂̒��Ŏx���@�ւ͕ی����E���_�ی������Z���^�[����s�撬���ւ̍L�����F�߁A�x���E�A�g�̌���E�ۑ�ɂ��Č������s�����B�Ȃ��AC���C�́A�Ђ�������n��x���Z���^�[�S���A�����c���Ƃ̍����ʼn��R�s�ɂ����Ď��{�����B |
|||||||||||
|
���w��㥐��㐧�x�ψ��� �E�ߘa6�N�x�ɂ��Ă�,����ܔN�Ԏg�p����u�`�V���o�X�ƃL�[�X���C�h�̍��V�̂���,���������̓�����搶���������I�����C���ɂ�錟������J�ÁB���e�����肵���B�܂�,�w���u�K��ɂ�����Љ�A�Ɋւ���u�`�ɂ��Ă�,��N��゙����V�K�u�K3��ƍX�V�u�K9��,�v12���{�ψ�����n゙�[��゙�u�t�߂��B����Ɋւ��Ă�,���C���{�Z���^�[����ML�ł̏�L���s�����B�ȏ�ɂ�萸�_�ی������ɐe�a���̂����萸�_�Ȉ�̈琬�ɂ��Č��������B |
|||||||||||